
 |
|
 |
「雁の童子」と「インドラの網」の関係 |
「『雁の童子』と砂漠で発掘された有翼の天使」で述べたように、「雁の童子」は、大乗仏教の源流となっている地域であるタクラマカン砂漠のオアシス都市を舞台とし、その地域での天使の壁画の発掘をきっかけにして、雁の老人から須利耶圭に託されて育てていた雁の童子の前世の関係(須利耶圭の雁の童子は前世には親子で画家の須利耶圭が童子の壁画を描いた)が明かされ、雁の童子は天に帰っていくという物語である。それに対して、「インドラの網」は同じ西域でも空気の希薄なツェラ高原を舞台にしていて、主人公の「私」は、夜明けの高原を歩いているうちに、天の世界に入り込み、天人の姿を見たり、3人の天の子供たちに会ったりする。そして、この3人の天の子供らに会って、「私」はこの天の子供らが、「コウタン大寺の廃趾(はいし)から発掘された壁画の三人」であることを知る。ここで、「私」はこの壁画の発掘をした青木晃というものだということが読者に知らされる。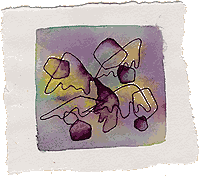 「雁の童子」では、童子の壁画を描いた画家が後生になって天から撃ち落とされてきた童子を育てることになるが、「インドラの網」では、天の子供らの壁画を発掘した学者が、天の世界に入り込んで壁画に描かれていた天の子供らに会う。しかも、壁画が発掘された場所として設定されているコウタンは、中国に伝わった華厳経の経典が秘蔵されていたオアシス都市なのだ。
「雁の童子」では、童子の壁画を描いた画家が後生になって天から撃ち落とされてきた童子を育てることになるが、「インドラの網」では、天の子供らの壁画を発掘した学者が、天の世界に入り込んで壁画に描かれていた天の子供らに会う。しかも、壁画が発掘された場所として設定されているコウタンは、中国に伝わった華厳経の経典が秘蔵されていたオアシス都市なのだ。このように、「インドラの網」では、「雁の童子」と同様に、大乗仏教の源流の地、天使の壁画の発掘、壁画に描かれた天の子供ら(童子)との出会い(離別)といった主題が結びつけられているが、それらの主題が「雁の童子」とは違った形で配置されていると言える。 |
|
| 華厳経とインドラの網 |
じつは、この物語のタイトルの「インドラの網」という言葉自体が、華厳経の世界を集約的に表す比喩なのだ。物語では、天の子供たちに「何しに来たんだい。」と聞かれて「私」は「あなたたちと一緒にお日さまををがみたいと思ってです。」と答える。 その後の高原の日の出の太陽の光の中を3人の天の子供たちが飛びまわる美しい場面でこの物語の最後に近い部分につぎの叙述がある。 「いまはすっかり青ぞらに変ったその天頂から四方の青白い天末までいちめんはられたインドラのスペクトル製の網、その繊維は蜘蛛(くも)のより細く、その組織は菌糸より緻密(ちみつ)に、透明清澄で黄金で又青く幾億互に交錯し光って顫(ふる)へて燃えました。」 この「インドラの網」というのは、華厳教を解説した「華厳五教書」などに出てくる言葉で、「因陀羅網境界門」というのは「インドラ神の網目の宝珠が無限に相即・相入しあっているような世界の教門」だという。相即とは要素が集まって一体化していること、相入とはAがBを入れ、BがAを入れるという入り組んだ関係である。つまり、網の結び目には宝珠が結ばれていて、その無数の宝珠がたがいに映しあうという関係が無限に続いていくというイメージだ。ひとつひとつの宝珠に宇宙が含まれ、そうした宝珠がたがいに関係しあうという大乗仏教の錯綜した宇宙観を表すメタファーだ。 |
||
| 視覚的印象と聴覚的印象の共振 | 賢治の場合には、「インドラの網」の複雑に入り組んだ関係を視覚的なイメージで捉えるだけでなく、さらに聴覚的な印象が重ねられている。子供らが飛びまわってぶつかりあうとともに、たくさんの太鼓が鳴っているのが「私」には聴こえるのだ。 「ほんたうに空のところどころマイナスの太陽ともいふやうに暗く藍(あゐ)や黄金(きん)や緑や灰いろに光り空から陥(お)ちこんだやうになり誰(た)れも敲(たた)かないのにちからいっぱい鳴ってゐる、百千のその天の太鼓は鳴ってゐながらそれで少しも鳴ってゐなかったのです。」 といったように、賢治は華厳経の入り組んだ世界を、視覚と聴覚が共振する複雑なイメージで捉えている。 |
||
| 華厳教の源流の地、コウタン |
このように「インドラの網」は、華厳教の世界と強いつながりをもつと考えられる。とすると、賢治が「インドラの網」で、3人の天の子供の壁画が掘り出された場所をコウタン大寺の廃趾という設定にしている理由も、コウタンが華厳教の源流の地であるからだと思われる。 つまり、「雁の童子」や「インドラの網」に出てくるガンダーラ風の天の童子の壁画のもとになっているのは、オーレル・スタインが発掘した有翼の天使だと考えられているが、これが発掘された場所はミーランであって、コウタンではない。一連の発掘の中で、スタインはコウタンでも発掘をし、貴重な成果を得ているが、天使の壁画は掘り出していないようだ。 | ||
|
※ 読み:コウタン、ウテン |
そうすると賢治が物語の中で天の童子が掘り出された場所をコウタンに設定したのは、コウタンにこだわる理由があったからだと思われる。現在では、コウタンが華厳経の成立の地ではないかという説が有力になっているようだが、華厳経が最初に漢訳される際にも、華厳経は西域のウテン国(※漢字ではコウタンと同じ字)から入ったことはもともとよく知られていた。ウテンで大乗仏教がさかんだった紀元400年ころに、漢人の支法領(しほうりょう)がウテンに滞在した時、国外に持ち出すことが厳禁されている大乗経典が秘蔵されていることを知り、中国にぜひそれを伝えたいと熱心に望み、国王に許されて、華厳教の前分の梵本を長安に持ち帰った。これをカシミールから招かれた僧の仏駄跋陀羅が漢訳したという(鎌田茂雄「華厳経物語」大法輪閣)。 賢治はこうしたことを知っていただろうから、天の童子の壁画が掘り出された場所をコウタン大寺に設定したのは、コウタンを華厳経が中国に伝わる源流の地とみなしたからなのだろう。 |
 |
ちくま文庫「宮沢賢治全集 6〜『インドラの網』」より この作品に関するコラムへ 1 2 |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||