
 |
|
 |
「春と修羅・序」の自負 |
「春と修羅」の詩が描かれたのは、妹の死をはさむ、賢治にとっての精神的な危機の時期である。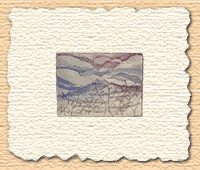 「心象スケッチ」という方法で、心象のあり様を直視し、記録することを通じて、心の危機を対象化し、克服していったとも言えるだろう。そして、こうした心象の記録の試みの積み重ね通じて、斬新な哲学的な視点をえたという自負を賢治はもった。 「心象スケッチ」という方法で、心象のあり様を直視し、記録することを通じて、心の危機を対象化し、克服していったとも言えるだろう。そして、こうした心象の記録の試みの積み重ね通じて、斬新な哲学的な視点をえたという自負を賢治はもった。「春と修羅・序」では、こうした哲学的な視点を、とぼけた、ユーモラスな語り口の詩の形で表明した。ここでは、ラディカルで、野心的な哲学的な問題意識が、遠回しで暗示的な表現で描かれている。あまりに、迂遠な形で提示しすぎたこともあって、彼の議論は同時代人にはほとんど理解されなかったようだ。現代の読者にとっても、「序」は、魅力的な部分はあちこちにあるが、結局、何を言いたいのかを読みとるのは困難な迷路のような詩である。 |
| 「「すべて」と「わたくし」と「みんな」 | 「序」の中でも、一番、ユーモラスで壮大、かつわけがわからないのは、つぎの部分
だ。
「これらについて人や銀河や修羅や海胆は/宇宙塵をたべ または空気や塩水を呼吸しながら/それぞれ新鮮な本体論もかんがえませうが/それらも畢竟こゝろのひとつの風物です」
銀河は宇宙塵をたべ、人は空気を呼吸し、海胆は塩水を吸いながら、それぞれが「俺は本当に存在するのだろうか」などと考えるけれど-----といった何とも途方もない話だ。
(すべてがわたくしの中のみんなであるように/みんなのおのおののなかのすべてですから )
この論理学の練習問題のようなややこしい命題は、華厳経に出てくる「インドラの網」のモデルを思い浮かべると合点のいくものになる。「インドラの網」は、世界を構成する要素の相互依存関係を現すモデルで、インドラの網の結び目には無数の珠玉があり、それぞれの珠玉はたがいに映しあい、ひとつひとつの珠玉には、世界全体が映されているという。このモデルと対応させると、「すべて(=all)」は全体としての世界であり、「みんな(=everyone, everything)」は無数の珠玉ということになり、「わたくし」もひとつの珠玉である。
とすると、この節の前半の「人や銀河や修羅や海胆」も、珠玉つまり「みんな」に対応すると考えるのが自然だろう。そう考えると、「銀河は宇宙塵をたべ、人は空気を呼吸し、海胆は塩水を吸いながら、本体論を考える」という途方もない話は、「みんな」がそれぞれの仕方で自分をとりまく世界と関係し、それぞれの仕方で世界について認識すると言っていることになるだろう。 このように、「序」では、ある時点での世界の認識について、多様な認識の仕方、認識の視点があることが強調され、心象スケッチが記録する「わたくし」にとっての「心の現象」は、ひとつの視点からのひとつの仕方での世界との関わりあいであることが示されている。 |
|
| 記録や歴史 地史の覚束なさ | では、異なる時点の間の世界の認識についてはどうだろうか。認識の時間的なつながりという点については、「序」の冒頭の「わたくしといふ現象は------」というところから、微視的な現象のつらなりと「わたくし」の関係が問題にされている。 「わたくしといふ現象」を記録した心象スケッチには、時間をどう扱うかという問題がつきまとっている筈だ。「二十二箇月の/過去と感ずる方向から/紙と鉱質インクをつらね」て「心象スケッチ」を書きついだものの、「わたくし」は、前の時点の「わたくし」とはそうとは意識しないままに変わっているということが、「正しくうつされた筈のこられのことばが/----/すでにはやくもその組成や質を変じ」というところで示唆されている。 そして、話は、大きな視野から見た認識の時間的な連なりに転じる。
「けだしわれわれがわれわれの感官や/風景や人物をかんずるやうに/そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに/記録や歴史 あるいは地史といふものも/それのいろいろの論料(データ)といつしよに/(因果の時空的制約のもとに)/われわれがかんじてゐるのに過ぎません」つまり、心象スケッチによって記録される「心の現象」が覚束ないのと同様に、「歴史あるいは地史」といった学問や科学の真理も動じやすいものだというのだ。 「記録や歴史 あるいは地史」はある時代の人たちにとって確かな真理であるように見なされるかもしれないが、それは論料(データ)を解釈する枠組みをその時代の人たちが共有しているためにすぎず、時代が変わるとその枠組みも変わってしまい、論料(データ)の解釈も大きく変わってしまうと賢治は言おうとしている。 |
|
| 共時的、通時的な認識批判 | このように賢治は、一方では、ある時点での世界の認識について、人の視点とそれ以外の生き物や動的なシステムの視点といった多様な認識の視点が共存することを指摘し、他方で、異なる時点の間の世界認識の変化について、時代とともに人々の間で共有される解釈の枠組みが変わるために世界のイメージが大きく変わってしまうという問題に目を向ける。 つまり、共時的な認識と通時的、歴史的な認識の両方について、大きな文脈からの認識についての批判の視点を示している。普通に人々があまり疑わずに依存している、認識を秩序だてる枠組みは、じつは移ろいやすく、きわめて頼りないことが強調されている。 |
|
| 「心象観察官」としての姿勢 | 「序」では、このように言わば大風呂敷を広げた議論をしているのだが、結局、「心象スケッチ」は何をめざしていると言っていることになるのだろう。
「心象スケッチ」という言葉で示される賢治の姿勢は、自らを「心象観察官」に任じたということだ。「心象観察官」というのは、賢治が詩のタイトルに使っている「風景観察官」という言葉を少し変えたものだ。「心象観察官」は、経験するさまざまな事象を「心の現象」として観察し記録する「観察者」であろうとする。経験を観察し記録するということと経験する事象を「心の現象」として観察し記録するのとは同じようだが、じつは大きな隔たりがある。単に経験を記録するという場合には、経験するモノやコトが「心の現象」という経路を通じて私に現れているということはとくに意識しない。しかし、経験する事象を「心の現象」として観察し記録するという場合には、外部の世界と「心の現象」とはどういう関係にあるのか、という問いかけがつねに含まれることになる。「心象観察官」は、そういう問いを強く意識した観察者なのだ。 |
|
| 感覚や認識を秩序だてる枠組みの多様さ | こうした「春と修羅・第1集」の心象スケッチのつみ重ねを通じて、「序」で述べられているような、大きな文脈からの認識批判の視点が生まれてきたのだと思われる。 つまり、同時代の人々があまり疑うことなく依存している感覚や認識の枠組みにとらわれず、感覚や認識を秩序だてる視点や枠組みは多彩であることを知ることが必要であり、そうした多元的な秩序を包み込むような視点をめざさなければならない、というのが「序」で賢治が言おうとしたことだと思われる。 「序」の最後の部分の「すべてこれらの命題は/心象や時間のそれ自身の性質として/第四次延長のなかで主張されます」という宣言は、そういうメッセージとして読むことができる。 特異な感覚の持ち主であった賢治は、同時代の人たちが常識と感じる感覚を安んじて共有することができなかった訳だが、そうした条件をつきつめることによって、こうしたラディカルな批判的な認識に行き着くことになった。 |
 |
ちくま文庫「宮沢賢治全集 1〜『春と修羅』」より
→「春と修羅・第1集」の心象スケッチと「青」へ |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||