
English
狐の小学校 |
English 狐の小学校 |
 |
現実にありそうな話からファンタジーへの移行 |
農学校の教師である「私」が、火山弾の手頃な標本をとるためと、浜茄(はまなす)が生えているといううわさの真偽を確かめるために茨海(ばらうみ)の野原にでかけるという、いかにも実際にありそうな話から始まって、「私」が狐の小学校を参観するという現実には起きそうもない世界に入りこんでしまう。 こうした現実から空想の世界への移り行きを、ごく自然な心の出来事として語る工夫がさまざまな形でなされているのが、賢治作品の大事な特徴のひとつだ。 |
| 野原で遠くから聴こえる学校のベル 狐の小学校の授業参観 |
茨海の野原を半日歩いて、火山弾はひとつ拾ったものの浜茄は見つからず、「私」は空腹をおぼえ、背嚢(はいのう)からパンを出して食べようかと思いながら、水のある所を探す。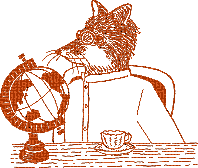 なかなか見つからず諦めてパンを食べようとした時に、「ずっと向ふの方でベルの鳴る音」を聞く。それは学校のベルの音のようだが、こんな所に学校があるわけがないと思っていると、こんどは子供たちのがやがやいる声が聞こえてくる。「少しの風のために、ふっとはっきりして来たり、又俄(には)かに遠くなったりしました。けれどもいかにも無邪気な子供らしい声が、呼んだり答へたり、勝手にひとり叫んだり、わあと笑ったり、……」という様子にひかれて、「私」は声の方に走っていく。わなのように結んだ草に足をとられてころぶと、どっと笑い声が起こり、「狐の子どもらがチョッキだけ着たり、半ズボンだけはいたり、たくさんたくさんこっちを見てはやしてゐる」のが見える。やがて、黒のフロックを着た先生の狐が現れ、狐小学校の授業を参観することになる。 なかなか見つからず諦めてパンを食べようとした時に、「ずっと向ふの方でベルの鳴る音」を聞く。それは学校のベルの音のようだが、こんな所に学校があるわけがないと思っていると、こんどは子供たちのがやがやいる声が聞こえてくる。「少しの風のために、ふっとはっきりして来たり、又俄(には)かに遠くなったりしました。けれどもいかにも無邪気な子供らしい声が、呼んだり答へたり、勝手にひとり叫んだり、わあと笑ったり、……」という様子にひかれて、「私」は声の方に走っていく。わなのように結んだ草に足をとられてころぶと、どっと笑い声が起こり、「狐の子どもらがチョッキだけ着たり、半ズボンだけはいたり、たくさんたくさんこっちを見てはやしてゐる」のが見える。やがて、黒のフロックを着た先生の狐が現れ、狐小学校の授業を参観することになる。野原でどこかから聴こえているような、いないような音にじっと耳を傾ける。そんな誰にでも覚えがある聴覚体験についての繊細な記述を追っていくうちに、現実から空想の世界へすんなり入りこんでしまうことになる。 |
|
| 心の中の本当の体験としてのファンタジー | この体験は、狐にだまされたわけでもなく、偽(うそ)でもないと「私」は語る。「狐小学校があるといってもそれはみんな私の頭の中にあったと云ふので決して偽(うそ)ではないのです。」 「注文の多い料理店」の広告にも書かれているように、架空のつくり話ではなく、実際にそんなふうに感じた心の中の光景がもとになっていると「私」とともに賢治も言いたいようだ。 |
 |
ちくま文庫「宮沢賢治全集 5〜『茨海小学校』」より この作品に関するコラムへ 1 |
||||||||||||||
 |
|
|
|
||||||||||||