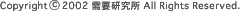|
|
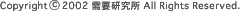
|
「春と修羅」第1集の詩では、地質学や気象学、植物学の用語がたくさん使われていることが同時代の文学者たちを驚かせた。 「春と修羅」について、賢治は若い友人への手紙の中で「心理学的な仕事の仕度」の「心象スケッチ」だと述べている。この「心理学的な仕事」とは、ひとつの仮説として「心象の時空の探究」だったと考えてみることができる。 賢治にとって心理学とは、心の科学的な研究であったようだ。そして、「春と修羅」第1集は詩であると同時に、心の科学的な研究のための「心象の時空の探究」のための心象スケッチでもあったと考えられる。 この心象の時空を描きだすために、地質学や気象学の用語が駆使される。つまり、心の科学の準備あるいは詩のために、自然科学の用語がメタファーとして活用される。このように独特の形で、領域をこえて用語が転用され、しかも、奇をてらってそうした訳ではなく、起きるべくしてそうした異なる領域の結びつきが起きている所に、賢治のすぐれた創造性が認められる。(心象スケッチと幻想)
賢治が感じていた時空は、古典物理学的な等質な時空とは、著しく異なるものだった。地上の人間が普通に生きている「わたしたちの空間」とは異なる異空間があって、時空の窪みのような所を通じて、異空間に入りこむという感じを賢治はもっていた。
等質な時空ではなく、異質な時空の入り組んだ心象の時空という感じ方は、賢治がしばしば幻想(幻覚)を体験したこととも深い関係があると思われる。幻想の経験は、賢治に恐怖を感じさせたが、またある場合には、幻想を通じて現れる尊い者との出会いを可能にした。 ユリアとペムペルと同じ存在かどうかはわからないが、「青森挽歌」では、天上の尊い生物である「巨きなすあしの生物たち」が描かれている。妹のトシの死の翌年、妹の影を追うようにして北に向かって旅した時の日付をもつ「青森挽歌」で、賢治は、死んだ妹がどこを通ってどんな所に行ったと感じられるかを執拗にたどっている。そしてトシがいったと感じられる天上にも、「また瓔珞やあやしいうすものをつけ/移らずしかもしづかにゆききする/巨きなすあしの生物たち」という表現が出てきて、賢治は天上にも尊い元型的な生物がいると感じていることがわかる。「ひかりの素足」という物語からわかるように、賢治にとって、白くひかる巨きな素足は如来の属性でもある。(「地質学の太古と元型的な生き物のイメー ジ」) このように、賢治の詩や物語では、地質学的なメタフアーが頻繁に用いられるが、注目すべきなのは、「発掘」というメタファーが、現在から見た過去について語る時だけでなく、未来やそれと置き換え可能な関係をもつらしい天上の異空間について語るためにも、よく使われるということだ。 たとえば、「春と修羅・序」の終わりの部分で「おそらくこれから二千年もたつたころは/それ相当のちがつた地質学が流用され/--------/新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層/きらびやかな氷窒素のあたりから/すてきな化石を発掘したり/あるいは白亜紀砂岩の層面に/透明な人類の巨大な足跡を/発見するかもしれません」と書いているように、未来について語る場合にも、地質学的な発掘というメタファーが使われている。未来には、地上ではなく「気圏の上層」で発掘をしているだろうというのだ。
「銀河鉄道の夜」の「プリオシン海岸」では、気圏のいちばん上層で発掘するというイメージが転じて、銀河のほとりで、大学士が牛の先祖の骨を掘り出したりしている場面になっている。これは、「イギリス海岸」に書かれている賢治が経験した泥岩層からのクルミの化石や偶蹄類の足跡の発掘が変奏されて「銀河鉄道の夜」の一場面になっている部分である。
さらに、賢治の物語と詩では、この天の子供たちも考古学的な発掘と結びつけられている。
これは、大乗仏教の歴史と縁の深いタクラマカン砂漠から天使の壁画が発掘されたという話と自分の幻想から現れる天の子供の元型的なイメージが結びついて、賢治は深い感銘を受けたためではないかと思われる。 こうした例からもかわるように、地質学的、考古学的なメタファーは、賢治にとって心象の時空を言語化するために不可欠の方法だったと考えられる。 |
|
|